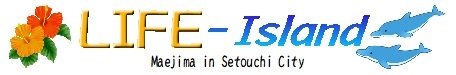「牛窓甘藍」*は自治体と地元農協が協力して瀬戸内市のブランド化し、全国展開しようと頑張っているキャベツです。 ≫ more牛窓甘藍 牛窓甘藍は、タキイ種苗のTCA422という晩生(おくて)の交配種です。 ≫ 閉じる
「第64回全日本野菜品種審査会(夏まき冬どりキャベツの部)」でタキイ交配『TCA-422』が1等特別賞。低温肥大性、在圃性にすぐれ、立毛では耐倒伏性、揃い性にすぐれました。収穫物では玉の形状が安定し、立毛、収穫物ともに最高の評価をいただき高得点を得ました。 タキイ種苗株式会社ホームぺージより引用
生で食べても甘く、わが家ではレンチンして塩コンブとごま油を掛けて毎日食べました。たくさん食べられてビールのつまみにもお勧めです。菌核病*に弱く栽培は大変ですが、見た目も緑鮮やかで気に入った品種なので、毎年沢山作付けしました。 ≫ 菌核病とは ≫ 閉じる
キャベツの菌核病は、気温15~20℃で湿気が高い条件で繁殖しやすく、結球始め頃から外葉の下から白色綿状の菌糸が発生し淡褐色~灰褐色の病斑となりやがて結球全体を腐敗させ、最後には黒色でネズミの糞のような菌核を作る。これらを放置すると子のう胞子が飛び散りさらにキャベツを犯していく、また土中で何年も潜伏する。
対策
・発生したら菌核を作る前に病変の株を圃場から出し深く埋めるなどする。
・殺菌剤などの薬剤散布を行う。
・圃場管理は、天地返し、連作を避けるなど発生させないよう管理する。
・菌核は湛水すれば速やかに死滅するので、夏期に圃場を湛水する。
この記事は、そんなキャベツの牛窓甘藍の種まきから収穫までの農業体験記です。
キャベツを作ろうとされる人の参考になればと思います。
(2017年8月~2018年4月の農業日誌から記事を起こしました)

目次 ≫
播種・育苗(8月初旬~9月初旬)
キャベツの播種(はしゅ:種蒔き)は野菜用セルトレイを使い、発芽後はビニールハウスで育苗し定植(畑に植える)まで管理します。
播種(8月初旬)
2017年8月初旬、140セルトレイ(200穴/1セルトレイ=28,000粒)を播種しました。
土は、与作N-150(全農が販売)という育苗培土を使用しました。
セルトレイに土入れ
セル箱にセルトレイを重ね、セルトレイに育苗培土を充填し、十分水分が馴染むよう灌水します。(底穴から水が流れるのが目安)
播種
セルの中心に5㎜ほどのくぼみをつけ、種を1粒づつ播種します。(種まき機使用)
表面に平らになるよう育苗培土を被せます。
発芽待ち
セルトレイに乾燥しないよう育苗培土の空き袋を流用してカバーし、発芽まで静置します。
周囲の積算温度にもよりますが大体2日半後に発芽が始まります。
発芽を確認したら設置
発芽の始まりが確認出来たらカバーをはずし、ビニールハウスの育苗台に移動し並べます。

育苗環境の4つの注意点
育苗では水やりや防除以外に環境管理の4つの注意点があります。
1.高床式設置
育苗箱を直置きしないようブロックと垂木で育苗台を設けます。
セルトレイ底部を空気にさらし根鉢形成の促進と病害虫予防になります。
2.通気・遮光
真夏の直射日光で苗が焼けないよう寒冷紗等で和らげ、通気・遮光などの調節をします。
3.防虫ネットで保護
ビニールハウスの開けた側面・扉は、飛来する野鳥、昆虫などで苗箱を荒らされないようネットで覆います。
4.苗箱の入替
苗箱の苗全体に日光が均等に当たるよう数日毎に位置入れ替えをします。
灌水(水やり)(定植まで毎日)
水やりは、定植まで毎日朝はたっぷり、晩は土が乾かない程度にやりました。
ポイント
・育苗培土によって、水持ちに違いがあるので注意が必要。
・細菌、ウィルスの感染の予防のためには水道水が、良い。
・夜に水分が多いと徒長しやすいので、水やりは朝に行う。
防除(8月初旬~中旬)
防除初回
本葉が出そろったころ、コナガ、ヨトウムシの予防で、オルトラン粒剤を株元に散布し、灌水します。
・その後コナガが発生したため、アディオン乳剤 希釈2000倍を散布しました。
定植前の防除(2回目)
定植前日に予防のため害虫全般に効用のベリーマークSC 希釈400倍 + 病害予防のオラクル粉剤 希200倍をセルトレイ1枚あたり500㎖灌注します。
ポイント
・苗は、虫、鳥、菌、ウィルスなど敵が多いので毎日監視し、異常があれば即対処しないと全滅の恐れがあり、育苗は手を抜けない大事な工程です。
・苗立枯病の注意
苗立枯病は、ピシウム属菌、リゾクトニア属菌というカビが原因で、育苗期~定植直後に胚軸の地際部から侵され、くびれていき褐色や白色に腐敗し苗全体がしおれて枯れていく病気です。
ピシウム属菌は水を介して伝染するのでセルトレイ育苗で広がりやすいので、育苗時は、セルトレイ底面の水はけを良くし、水やりには水道水を用います(塩素消毒効果)。圃場では、畝を高くし水はけを良くして予防します。
発生した苗は、取り除いて伝染を防ぎます。特にリゾクトニア属菌は、発病した苗以外で圃場で株腐病を発症し伝染した経験をしました。発生したセルトレイは別管理として、定植も他の苗とは隔離するのが最良。防除は専ら予防として行います。
農薬:ピシウム属菌予防=フォリオゴールド、リゾリクトニア属菌予防=バリダシン液剤5、アミスター20フロアブル、シグナムWDGが登録されている。
露地栽培(8月中旬~4月)
土壌調整と圃場準備(8月中旬)
定植の2週間以上前から圃場の準備を始めます。
土壌診断の結果
JA岡山の働きかけで土壌診断を受けた結果、pHは高く、石灰、リン酸、カリが過剰、微量要素、腐植が低水準でした。これは、この地域の鶏糞の積年の慣用によるものです。鶏糞は窒素の肥効が高く、葉物野菜がよく育つので安価で効果的な肥料として多用されたのでした。また、石灰の連用も高いのです。
私の借用した圃場も例外に漏れず、また、農業の師匠は鶏糞を人一倍多様する人でした。
土壌調整
8月初旬、従来からの鶏糞使用を中止し、牛糞へ切り替え、苦土石灰の散布を控えて土づくりを行い、土壌改善を目指します。
天地返し
キャベツの連作を行っているため、プラウを使った天地返しが必要です。
8月初旬、プラウがないので、ロータリーで最大限の深耕をしました。
溝切
前島の圃場は、大半が傾斜地で雨水の逃げ道を設けておかないと、大雨で畑が流れてしまいます。


2018年の台風直撃で、植えたばかりのキャベツの苗が流れた
定植準備と基肥(8月下旬)
土壌調整、圃場の準備が終わり定植直前に発芽してしまった草を除き、基肥を施肥します。
除草
圃場内の種を持った草は抜いて外に出します。定植しない圃場の縁は、除草剤バスタかプリグロックスLを散布しておきます。
基肥
8月下旬、牛糞500㎏/10a、化成肥料=スミカエース1(化成18-10-14)120㎏/10a、微量要素30㎏/10aを圃場全体に散布し、ロータリーで耕うんし、縁は鋤簾(ジョレン)で縁上げして整地します。
定植(9月初旬)
定植(圃場への苗を移植)
定植は、師匠の全自動移植機をお借りして行いました。
畝は全自動移植機のタイヤ幅調整の轍で出来、55㎝にセットし、株間28㎝で植え付けます。
この移植機は、平地では性能を十分発揮し反*当り2時間以下で植え付けを完了できます。その名のとおり手を放しても真っ直ぐな軌跡できれいに自動で植えていき圃場の端の折り返しも思い機体も片手で難なくできます。*1反 = 300坪 ≒ 10a = 991.74㎡
ところが、前島はほとんどが斜面です、便利な機械はたちまち危険な凶器です。何度も危ない目に逢い圃場の端の絶壁では死ぬ思いをします。師匠も3度崖から機械を落としたそうです。

防除
ヨトウムシ、ネキリムシ予防のダイアジノンを圃場の縁近く1m帯状に散布、ナメクジ予防にマイキラー希釈200倍ー100ℓ/10aを圃場の縁に散布します。
灌水
スミサンスイ(灌水チューブ)にて、1時間30分程度充分に水やりします。ただし、定植の直近に雨が降り土に十分水分を含んでいる場合は灌水しません。
除草剤散布
1シーズンでも耕作放棄された圃場は、雑草のタネが大量に残っていて苗の成長と共に芽吹きとても厄介です。キャベツ定植時に使える選択性の除草剤があるので利用します。
・定植後すぐに雑草発芽前、スベリヒユなどの雑草に効用:フィールドスターp 希釈2000倍ー100ℓ/10a。
・イネ科雑草の発芽後5葉まで効用:ナブ乳剤 希釈600倍-100ℓ/10a。

灌水、草取り(9月中旬~10月中旬)
灌水(カンスイ:水やり)
定植後2週間日照りが続いた場合には、スミサンスイで灌水します。
前島では雨は、8月は全く降らないですが9月に入るとよく降るので、定植後に灌水した経験はほとんどなく6年間で1度のみでした。
前島の名人の教え:「土を10cmほど堀起こして、片手で握って固まれば土の水分は大丈夫、ばらけ落ちる様なら水やりが必要。」勿論土壌にもより異なりますが、長年の経験が物語る良い教えです。要は、無闇に灌水すると発育不良や病害の素ということです。 日照りが続き土表面が乾き日中苗が萎えて見えて、水やりすべきか否か悩んだとき、当時90歳になるユウジさんに水やりのタイミング目安をうかがったら、しばし考えた後のお言葉でした。
草取り
雑草は作物の成長を阻害し、害虫に棲家を与えます。露地野菜の農業は雑草との闘いです。雨の後は芽吹いた草をこまめに抜くことが必要なのです。こちらの圃場の草を採っている間にあちらの圃場の草は伸び、取り終えたと思い次の圃場の草取りを始めていると最初の圃場でまた草が出てくる。いつまでもいたちごっこです。
農業で草取りが一番つらい仕事だったかもしれません。
名人ユウジさんの奥さんは草取りがすごいです。彼女の草取りのスピードもさることながら、その後生えてこないのです。やっぱりかないません。
病害虫防除初回(9月中旬)
農薬散布:ファルコンエースフロアブル 希釈2000倍 100ℓ/10a コナガ、ヨトウムシ、アオムシの防除をします。
9月は、害虫のピークです。毎日圃場を見回り、見つけたら即対処が必須です。圃場内、圃場周辺の雑草も害虫の温床となるので小まめに草刈りを実施します。
害虫は、ネキリムシ、ハスモンヨトウ、コナガ、キスジハムシ、ハイマダラメイガ、オオタバコガ、アブラムシ
農薬は、収穫までの使用期限(農薬の残存期間)、使用間隔、回数制限、希釈を確認し必ず守らなければなりません。
病害虫防除2回目(9月下旬)
農薬散布:➀アディオン乳剤 希釈2000倍ー100ℓ/10a アブラムシ、コナガ防除、➁ダコニール1000 希釈1000倍-100ℓ/10a べと病などの病害防除します。
台風等による大雨の後は特に、べと病、軟腐病、黒腐病、菌核病、萎黄病などの病害が発生し易いので、水利の管理、ダコニール1000、フォリオゴールド、バリダシン等の防除が必要。病気が発生した圃場は、収束後次の作付け前に土壌消毒などの対策することが大事です。
追肥初回・中耕(9月下旬)
苗の本葉が4~5枚に育った頃、追肥します。
追肥、中耕
スミカエース1(化成18-10-14)100㎏/10a、アグリハーモニー(微量要素)20㎏/10aを畝間に帯状に散布し、管理機(小さな耕運機)ですき込みます。
土寄せ
畝幅に合わせて土寄せ機を管理機にセットし、株元に土寄せします。病害の予防、雑草の抑制、作物の動揺を押え強く育てる効果があります。
スミカエース1号成分:窒素全量18%、アンモニア態窒素10.5%、硝酸態窒素7.5%、りん酸10%、カリ14%、DCS0.3%
病害虫防除3回目(10月初旬)
農薬散布:ランネート45DF 希釈1000倍ー100ℓ/10a アブラムシ、コナガ防除
毎回機能の違う種類の農薬を使用します。
追肥2回目(10月中旬)
結球の初期に、外葉を傷つけないよう注意しながら、追肥します。外葉が旺盛になり土壌との混和は難しいので雨で浸み込むのを待ちます。
追肥:スミカエース 80㎏/10a アグリハーモニー 30㎏/10a カルミンS 20㎏/10a
病害虫防除4回目(10月下旬)
農薬散布:➀プレバソンフロアブル5 希釈2000倍ー100ℓ/10a コナガ、ハイマダラメイガ防除 ➁ダコニール1000 希釈1000倍-100ℓ/10a べと病などの病害防除
最後の防除です。11月に入ると害虫の活性は下がります。ただし、黒腐病、菌核病は翌年まで病害するので要注意です。
収穫の2か月前で、薬剤の散布を終了させます。農薬の残効を出荷前に完全に除去するためです。後は、ヒヨドリ、ヌートリアの襲来や、病虫害発生を見回りながら、結球し肥大し玉が締まり重くなるのをじっと待ちます。
株腐病の注意
リゾリクトニア属菌による病気です。収穫間近の結球部の側部~下部に黒褐色の水浸状の病斑が表面に広がり、展開している外葉部には発病しない、湿気が多いと進行する様です。育苗中に発生し、圃場で伝染することがあります。
対策は、畝を高くし排水を良くします。発生した株は圃場から外に出し、土壌中に伝染源を残さないよう努めます。
農薬:播種・育苗の農薬に同じ。
鳥獣害予防
ヌートリア
前島では、近年ヌートリアという特定外来生物で大型のねずみ種が繁殖し、作物を食害します。
湿地の近い圃場は、縁に金属の防獣ネットを設けます。罠を仕掛けて捕獲すると自治体から報奨金が出るらしいのですが、殺生は苦手なので無理です。
ヒヨドリ
前島は、12月に入ると、渡りのヒヨドリが集団で飛来し、キャベツを食害するだけではなく、糞で玉を汚します。圃場全体に防鳥ネットを掛けて、杭で浮かせてキャベツに接触させないようにします。
牛窓甘藍は、外葉が大きく立ち上がる草勢のため、他の品種のキャベツを先に食害し、後から食す傾向があることが観測されています。
イノシシ
前島では、対岸の錦海塩田跡地のソーラー発電開発のため、棲家を追いやられたイノシシが泳いで渡り、住みつき繁殖しています。電気柵もお尻から入り荒らすので効き目なしの情報アリ。ホームセンターで手に入るコンクリート基礎用の金属ネットで柵を設けます。
収穫(2月下旬~4月上旬)
本格的な収穫は、2月下旬になってからです。それまで、縁の肥大化した株を抜き取りしながらゆっくりと待ちます。
抜き取りは、結球の熟度の見極めに熟練を要し、採ってみたらスカスカで軽かったということが何度もありました。それに、生長中の株を傷めないように収穫したキャベツを注意深く運ばなければなりません。効率が悪いうえとても疲れる作業です。

本格収穫は全採りで圃場の端から収穫し、残った株や外葉をフレールモアですき込みながら、収穫します。
スッキリ気持ちよく、それに収穫したキャベツの積込も軽トラを乗り入れ直に横付けできるので楽です。

箱入れと出荷作業は、楽しいひと時でした。

まとめ
牛窓甘藍は、栽培するのは他のキャベツより1つ2つ余計に手間がかかりますが、穫れた玉は緑色の発色が他のキャベツより鮮やかで、出荷用の箱も専用の白く印刷された綺麗な箱です。特別なキャベツを育てたという満足感がとてもうれしかったです。それに、市場でも少し高値で取ってくれるのも楽しみでした。
就農中の秋冬作キャベツは、嵯峨緑2号(早生=わせ)、湖月SP(中早生)、牛窓甘藍(晩生=おくて)*、彩ひかり(晩生)の4種の生産を経験しました。早生~晩生の品種と播種時期、圃場毎の日照時間の違いを使い分けて、11月~4月まで順次収穫できるように努めました。



嵯峨緑2号は、10月初旬には外葉を展開し地面を覆いつくす草勢のため、同時期に旺盛になる雑草の抑止が出来るので、晩生を植えて草取りに苦労した圃場に充てるなど、現場ならではのノウハウも覚えました。ただ、早生種は、害虫の活発な時期に定植するため防除の油断が出来ません。農薬散布の数日の遅れで、圃場内の30%をヨトウムシに食害された経験もしました。
振り返れば、灼熱地獄の夏の畑で延々と草取りしたり、手が凍えひび割れる真冬の凍ったキャベツの抜き取り、重い収穫袋の運搬と辛かったことも今はいい思い出であり、学んだことの大きさに高揚します。