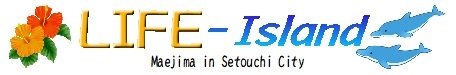前の住人が植えた梅の木です。移住当初は、ルビーロウムシが幹はもちろん小枝までびっしりついていて悩まされました。全く薬剤が効かないのです。へらやブラシで1つづつはがして3年目についに撃滅して、樹は元気になり実をつけるようになりました。
前の住人が植えた梅の木です。移住当初は、ルビーロウムシが幹はもちろん小枝までびっしりついていて悩まされました。全く薬剤が効かないのです。へらやブラシで1つづつはがして3年目についに撃滅して、樹は元気になり実をつけるようになりました。
目次 ≫
ウメ(梅)の四季
夏
2018年8月25日撮影

冬
2018年12月12日撮影


2018年12月12日 剪定しました。


2020年2月19日撮影


2019年2月 今年の花は、質素に咲いています。 剪定が強すぎたので仕方ありません。

ウメ(梅)のデータ
基礎知識
ウメの基本的な情報を押さえておきます。
原産地
中国、ベトナム。 日本へは奈良時代に渡来し栽培されたといわれています。ただ、弥生時代の遺跡発掘で種が見つかるなど未解明なことも多いようです。
学名
Prunus mume
(英)Japanese apricot
(別)コウモンボク(好文木)、(コノハナ)木の花、ハルツゲグサ(春告草)、ニオイグサ(匂草)、カザミグサ(香散見草)、カゼマチグサ(風待草)、コウバエグサ(香栄草)、ハツナグサ(初名草)、ハナノアニ(花の兄)
科名 / 属名
バラ科 / サクラ属 / スモモ亜属
名前の由来
漢方薬「烏梅(うばい)」の形で、奈良時代に中国から伝来、平安時代に広く普及し中国の発音がムメイから「むめ」、「うめ」の転訛の説、「熟実」(ウムミ)からの転訛の説などあります。
品種
梅は、大きくは花梅と実梅に分けられ特に花梅は園芸品種で見るとアンズやスモモと交雑され400種以上あるそうです。木の性質や花の特徴から「野梅系」・「緋梅系」・「豊後系」という3系統の分類法があるそうです。
実梅の種類からは以下のような品種があります。
ナンコウウメ(南高梅):和歌山県のブランド品種、粒が大きく皮が薄く肉厚、梅干し、甘露煮などで利用されます。
コジロ(古城):和歌山県のブランド品種、南高梅とり少し小粒、梅酒、梅ジュースに利用されます。
シラカガウメ(白加賀梅):関東地方で多く流通されている品種。肉厚で緻密な実、梅干し、梅酒、梅シロップなど。
アンズウメ(杏梅):杏と梅の交配種、酸味が少ない。
コウシュウコウメ(甲州小梅):山梨県で主に生産されている品種。小粒でカリカリした食感の梅干しにされます。
小梅では、他に長野県で生産されているリュウキョウコウメ(竜峡小梅)があります。
形態
落葉小高木
樹高
5m~10m
開花時期
1月~3月
耐寒性 / 耐暑性
強い・強い
用途
鑑賞用:盆栽、庭木、公園
薬用:未熟な果実を燻製にした烏梅(うばい)という生薬は、下痢止め、解熱、咳止め、去痰などに効果があるといわれています。青梅の搾り汁を濃縮した梅肉エキスは食中毒の薬として利用されています。
食用:実は品種や熟度によってさまざまな食用として利用されています。梅干し、梅酒、梅シロップ、梅じそ、ハチミツ漬け、青梅ピクルスなど。
染料:紅花から紅の色素を取り出すときに、梅のクエン酸をバンセンザイ(媒潜剤)として使いました。
特性
梅は冬に一時的な気温上昇で開花してしまう。
栽培メモ
ふやし方
種蒔き:7月~8月に熟した実から種を取り出し果肉を除いて、乾燥させないようビニール袋などで密閉し冷蔵庫で保管し、11月に種蒔きします。
種蒔きで育てると親とは異なる花が咲きます。苗木は、2年ほどで接ぎ木の台木として使えます。
接ぎ木:3月中旬から下旬に前年枝の穂木を5㎝ほど採り、台木に切り継します。
挿し木:品種によっては可能です。挿し木できるかどうかを事前に調べる必要があります。
栽培環境
梅が育つ温度は年平均7℃以上、日当たりのよく水はけのよい場所。
土づくり
鉢植えの場合、赤玉土小粒7:腐葉土3を混ぜたものなど。土はあまり選ばない。露地植えは、大きめに掘り上げた土と腐葉土を混ぜて埋め戻す。
植え付け・植え替え
11月~2月が適期。鉢植えの植え替えは、通気のため2年~3年に1回必要。
水やり
鉢植えの場合、土が乾いたらそこ穴から流れるくらいみずやり。露地植えの場合は、夏の日照りが続くときは水やりが必要。植え付け後2年は乾燥させないよう注意します。
施肥
露地植えは、7月に有機肥料を礼肥。結実が多いときは4月に化成肥料を追肥。鉢植えは2月、6月、9月に緩効性化成肥料か有機肥料を株元に追肥。
収穫
5月中旬~6月下旬
剪定
「桜切るバカ梅切らぬバカ」と言いますが、梅は剪定しないと枝が強く伸び株元の枝が枯れたり、樹形が整いにくいので、冬に枯れ枝、樹冠の内側に伸びた枝、ひこばえ、徒長枝などの不要な枝を選定します。
12月~2月が適期。6月~7月には徒長枝の切り戻しを行います。
強剪定は、枝が長く伸びて花付きが悪くなるので避け、枝の半分から1/3を残すようにします。
花芽は春の時より伸びた50㎝以下の枝に梅雨から夏にかけて花芽分化し翌春に咲きます。勢いよく伸びた徒長枝には花芽はつきづらいです。
枝の縦(垂直気味)に伸びる枝には花芽がつきづらく、横(水平気味)に伸びる枝は花がつきやすいです。
鉢植えの剪定は、花が咲き終わった直後に、花柄を取り、樹形を保つには残す葉目を確認しながら切り戻しします。
芽摘み
4月中旬以降に、強めの新芽が出て枝が長く伸びるので樹形を保つために、芽のうちに摘み取ります。
病害虫
プラムポックスウイルス(ウメ輪紋ウィルス):葉や果実に斑紋などの症状がでます。2009年東京都青梅市の梅郷で発生し大きな被害が出ました。アブラムシにより媒介され、モモ、スモモなどのバラ科の果樹に感染します。感染から発症までに3年もの潜伏期間があり、感染した梅の木を焼却処分にせざるを得ないようです。防除は、健全な苗を使うことと、アブラムシの防除を徹底することです。
黒星病:果実に黒い斑点が発生します。4月下旬~5月上旬にトップジンなどの殺菌剤で予防します。
ウメ潰瘍病:
アブラムシ:
カイガラムシ:
ウメスカシクロバ: