瀬戸内海の離島にある自宅の庭に作った400㎡に満たない畑で、いろいな野菜の栽培に挑戦し自給自足を目指しています。四季を通して病害虫や天候との闘い、失敗から学んだこと、成果を載せていきます。料理も紹介できればと思います。
目次 ≫
離島の菜園の野菜たち
野菜の名前をタップして記事をご覧ください。まだまだ少ないですが、チャレンジした野菜の生育と四季の容姿に合わせてのんびりマイペースで書いていますのでご容赦をm(__)m
土壌について学んだノート
農業を始めて、JAや県の普及センターの方々、文献、ネットなどでいろいろと学んだノートを記事にしました。
土性(どせい)
土性は、砂(粗砂、細砂)シルト、粘土の各成分の粒径組成によって示される土壌の性質
の一つで、砂にはその土壌の母材が含まれることが多く、粘土の中で、特に微細なものはコ
ロイド的な性質を持ち、表面積が大きく土壌中の化学反応に関与している。
粘土含量が多ければ保肥力の基である、陽イオン交換容量(CEC)も大きい。また、砂、
シルト、粘土の粒径組成の違いによって、土壌の可塑性や粘着性も変化する。
土性の決定
国際土壌学会法による土性の決定は、細砂、粗砂、シルト、粘土の4成分の百分率を定量し、砂=粗砂+細砂として粒径区分に基づいた土壌三角図表に当てはめ14の土性に区分する。
細砂、粗砂、シルト、粘土の区分は、国際土壌学会法による土壌粒子の大きさにより、区分されている。

土性区分

※壌質砂土及び砂壌土は、粗砂及び細砂の含量により次のように細分される。
①壌質粗砂土(LCoS) :細砂40%以下、粗砂45%以上
②壌質細砂土(LFS) :細砂40%以上、粗砂45%以下
③粗砂壌土(CoSL) :細砂40%以下、粗砂45%以上
④細砂壌土(FSL) :細砂40%以上、粗砂45%以下
土壌の塑性による判断と理化学的な特徴(土性区分と特徴)
土性の区分と特徴
土性三角図法

各土性の特徴
重粘土
国際法による粘土含量45%以上の土壌、可塑性、粘着性に富み、適当な水分があれば、指先でこねると、太さ2mm程度のひも状に彫塑できる。感触は、粘りが強くつるつるとした感じとなる。保肥力は高いが、排水不良で耕耘性低く明きょ、暗きょ等による排水が必要。
埴土
粘土含量25~45%の土壌で、砂の多いものを砂質、シルトの多いものをシルト質として名称に冠する (砂質埴土など)指先でこねるとひも状に彫塑でき、触感土性は粘りが強くつるつるとした感覚。
埴壌土
粘土含量は、埴土と壌土の中間で、15~25%の土壌で、砂の多いものを砂質、シルトの多いものをシルト質として名称に冠する。触感土性は、粘りがありつるつるとした感じと同時に、ザラザラとした砂の感触が少しある。
壌土
中間的な土壌で、粘土含量は0~15%、砂含量40~65%の土壌で、触感土性は、ザラザラとした砂の感じと、つるつるとした粘土の感覚が半々程度感じる。
砂壌土
砂と壌土の中間の土性で、粘土含量15%以下、砂含量65~85%の土壌で、触感土性は、ザラザラとした砂の感触とつるつるとした粘土の感触が少しある。砂質であるが砂そのものではなく、やや乾きやすい土。
砂土
粘土含量0~15%、砂含量85%以上を言い、触感土性は、ザラザラしており粘土の感触はほとんど無い状態。保水力、保肥力ともに低い土。
礫土
粒径区分で、直径2mm以上のものを礫という。風乾した土壌の中に礫が50%以上含まれる場合に礫土という。風化作用を余り受けていない角張っている礫は角礫という。農耕地には適さない土。
腐植土
土壌中の腐植含量が20%以上含まれ、黒色で軽しょうな土壌を腐植土というである。腐植土には、黒泥土と泥炭があり、泥炭土は植物遺体が肉眼的に判定出来るもので、黒泥土は判別できないもとして区分する場合もある。
土壌の化学性
植物の必須元素
主要素
植物の体を構成する元素

微量要素
植物の調整に働く元素

土壌中での養分の拮抗・相助作用
植物の養分には、1つの成分が過剰に在る場合別の養分の吸収を阻害・抑制する拮抗作用、他の養分の吸収が促進される相助(相乗)作用がある。

養分のバランスは、吸収時の拮抗作用等により微量要素の欠乏症などが発生することから重要であり、特に相互関係が多いCa、Mg、K(塩基類)のバランスを適正に 管理することは、各要素の吸収利用においても重要となる。 乾燥する畑では 養分吸収を適正にするためにも、塩類バランスには注意する必要がある。 一般には 当量比で CaO/MgO=6以下 MgO/K O=2以上となるよう管理する 。
土壌pH(土壌酸度)
pHが高い(7≧)と、鉄、マンガン、亜鉛等の微量要素が吸収しにくくなる。
pHが過度に高い(8.5≧)と、ホウ素が吸収しにくくなる。
土壌pHによる養分の溶解性

帯が太いと吸収しやすく、細いと吸収しにくい。

土壌溶液中のイオン
 作物に必要な養分を保持しながら適切に供給する機能を土壌は持っている。保持供給の 主体は土壌コロイドという土(粘土)と腐植等で作られるもので、塩基(養分など)を電 気的に結合(弱い結合)して保持される。
作物に必要な養分を保持しながら適切に供給する機能を土壌は持っている。保持供給の 主体は土壌コロイドという土(粘土)と腐植等で作られるもので、塩基(養分など)を電 気的に結合(弱い結合)して保持される。
陽イオン:カチオン=コロイドに吸着=交換性塩基 H⁺ NH⁺ Mg⁺ Ca²⁺ Na⁺
陰イオン:アニオン=アロフェン等に吸着 NO₃⁻ H₂PO₄⁻ SO₄²⁻ Cl⁻
土壌コロイドと置換しやすいカチオンの順位:H>Ca>Mg>K・NH₄>Na
植物の根は、弱酸を出してその水素(H)イオンで他の塩基を遊離させ吸収する。

CEC(Cation Exchange Capacity:陽イオン交換容量)とは、土壌コロイドが陽イオンを結合している腕の数。
塩基飽和度
陽イオン交換容量(CEC)の内、どれだけ塩基類(土壌関係では:Ca、Mg、K)が保持 されているかを表したもので、各塩基毎の飽和度とともに、全体(Ca、Mg、K)の塩基が 占める割合も土壌中の塩基状態を把握する重要な数値である。 下の図は、CECのイメージとして10個の塩基を保持できる土壌コロイドに対して、それ ぞれの飽和度を表しており、塩基飽和度130%の場合は、土壌が保持できず、流亡し易い塩 基が存在することを意味している。

出典元:農林水産省Webサイト( www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h…/ntuti4.pdf)抜粋・加工
腐植
腐植とは、土壌中で有機物(堆肥、作物残さ、土壌生物残骸など)が微生物によって分解されて生成された無定形の高分子化合物=腐植物質。生成された腐植物質はさらに分解されることによって無機養分の供給源となり、土壌の団粒形成を促進し、土壌生物の栄養源となる。
腐植物質が増えると、植物への窒素供給が増え、土壌の構造がよくなる。
腐植物質を増やす方法としては、稲わら、堆肥、作物残骸等をよくすき込み。

ヤンマーhpより引用(https://www.yanmar.com/jp/agri/agrilife/kitchen_garden/field/soil/)
土壌診断
土壌診断項目
実際の土壌診断方法、基準値、改良方法は、農林省のHPを参照する。
pH
EC
EC(Electric Conductivity:電気伝導度)は、土壌中の塩類濃度の目安。養分が多い状態だとECは高くなり、植物が水を吸い上げづらくなり、肥焼けを起こすこともある。
リン酸吸収係数
リンは、主要元素の1つで多くの野菜の生育で初期ほど必要、根の発達に関係が強く越冬の野菜はリン酸を初期に充分供給し、低温期に入る前に根を張らせることが重要。しかし、土壌に強く吸収され水に溶けにくい状態になり、長年の施用で過剰気味な圃場が多い。
可給態リン酸
主にトルオーグ法という測定方法によって求められるリン酸量。
CEC
塩基飽和度
有効態ケイ酸
有効態けい酸は、水稲栽培では非常に重要な指標。野菜類では、有効態けい酸量は対象外。
水稲は窒素の10倍以上のけい酸を吸収すると言われている。
土性
土を構成する粒の大きさの構成割合
土の粒は細かい粒(粘土)から荒い粒(れき)まで様々あり、土壌の性質はその粒の大きさと割合によって性質が異る。粒の大きさを所定の大きさに区分し、その組成を示したのが土性。土性の違いによって、土壌が肥料養分を保持する力が異なる。手で土壌を触ることによって、その割合をある程度把握している。
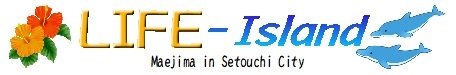






 エゴマ(荏胡麻)
エゴマ(荏胡麻) 